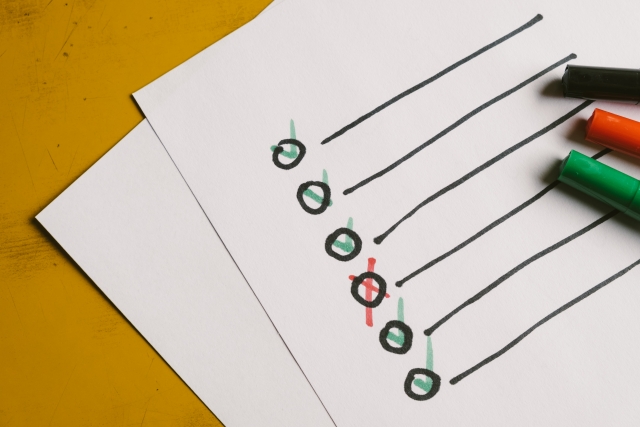「発達性協調運動障害」という言葉は、数年前まで発達の専門医であっても認知度が低い障害でした。
知的発達には遅れはなく、筋肉や神経、視覚、聴覚などにも明らかな異常はないのに、年齢に応じてできる動きに時間がかかる、ぎこちない、正確にできないといった状態です。
ポイントとなる4歳の体の動きはどんな感じなのでしょうか。
発達性協調運動障害と診断される4歳の体の動きは?

「つまずくものがないのによく転ぶ」「靴ひもがうまく結べない」など極端に不器用な子、運動の苦手な子が小学校のクラスに数人はいます。
今までは、運動不足や過保護に育てられたため、経験が少ないなどといったことが原因と思われていました。
ところが、これは「発達性協調運動障害(DCD)」である可能性が知られるようになってきたのです。
学童期になって気づくこともありますが、実は乳幼児期からその兆候があるのです。
「ミルクを飲むときにむせやすい」「ハイハイがぎこちない」などです。
幼稚園に入園する4歳になると、他の子との違いがはっきりとすることが多いです。
「言葉が不明瞭で聞き取りにくい」「塗り絵を線にそって、キレイに塗れない」「スプーン、コップがうまく使えない」「はさみがうまく使えない」「着替えが遅い、ボタンが苦手」「階段の昇り降りが何となくおかしい」といった日常生活の動きに気づくようになります。
発達性協調運動障害と診断された4歳の場合、どんなことに気をつければいい?

発達性協調運動障害の子供は、誰でも難なくこなせるような「片足でバランスを取る」「床にボールを弾ませる」などといったビックリするような動きをします。
これは、脳が運動を調整できないために起こる障害と考えられています。
発達性協調運動障害の子供は、普通に発達している子供のように運動など自然に上達していくことが難しいので、大人が介入していく必要があります。
しかし、できないことを何度も反復練習させても、挫折したり屈辱感を感じたりするだけです。
4歳くらいだと、いろんな動きを楽しく経験することで運動の苦手意識が低くなりやすいです。
家族で楽しみながら、公園のブランコ、アスレチックなどをすることもおすすめです。また、手先の運動に粘度遊びやブロックもいいです。
まとめ
発達性協調運動障害は、「運動が苦手」「手先が不器用」として見られがちです。
しかし、乳幼児期からその傾向があります。
発達性協調運動障害と診断されるのは、4歳の運動能力によって気づくことが多いです。
「なんだかうちの子、他の子と比べてとにかく不器用、動きがぎこちない」など感じたときは、専門医に相談してみることをおすすめします。